第4回柔道整復師国家試験の問題と解答を全て掲載します。
【午前問題】第4回柔道整復師国家試験
問題1 動脈血が流れる血管はどれか。
- 腕頭静脈
- 肺静脈
- 門脈
- 奇静脈
回答はこちらをタップ
2.肺静脈
問題2 正しいのはどれか。
- 右気管支は左気管支より太い。
- 左肺は3葉である。
- 肺の栄養血管は肺動脈である。
- 肺胸膜は粘膜である。
回答はこちらをタップ
1.右気管支は左気管支より太い。
問題3 腹膜後器官はどれか。
- 膵臓
- 肝臓
- 脾臓
- 胃
回答はこちらをタップ
1.膵臓
問題4 正しいのはどれか。
- 腎小体をネフロンという。
- 尿管には弁がある。
- 膀胱の筋層は平滑筋である。
- 尿道括約筋は外尿道口にある。
回答はこちらをタップ
3.膀胱の筋層は平滑筋である。
問題5 視覚伝達路の中継核はどれか。
- 線状体
- 台形体
- 赤核
- 外側膝状体
回答はこちらをタップ
4.外側膝状体
問題6 誤っているのはどれか。
- クモ膜は硬膜と軟膜との間にある。
- 脳室の脈絡叢は髄液をつくる。
- 錐体外路は知覚の伝導路である。
- 脳神経は末梢神経である。
回答はこちらをタップ
3.錐体外路は知覚の伝導路である。
問題7 正しいのはどれか。
- 副神経は頸神経叢から分枝する。
- 横隔神経は脳神経から分枝する。
- 坐骨神経は骨盤神経叢から分枝する。
- 尺骨神経は腕神経叢から分枝する。
回答はこちらをタップ
4.尺骨神経は腕神経叢から分枝する。
問題8 正しいのはどれか。
- 水晶体はカメラのレンズに相当する。
- 蝸牛は平衡覚に関与する。
- 味覚は舌下神経に支配される。
- 視神経乳頭は視力が最もよい。
回答はこちらをタップ
1.水晶体はカメラのレンズに相当する。
問題9 乳突蜂巣が存在するのはどれか。
- 篩骨
- 上顎骨
- 蝶形骨
- 側頭骨
回答はこちらをタップ
4.側頭骨
問題10 顔面神経の支配を受けるのはどれか。
- 側頭筋
- 頬筋
- 咬筋
- 外側翼突筋
回答はこちらをタップ
2.頬筋
問題11 肘関節にないのはどれか。
- 蝶番関節
- 楕円関節
- 球関節
- 車軸関節
回答はこちらをタップ
2.楕円関節
問題12 誤っているのはどれか。
- 鼠径靭帯は上前腸骨棘と恥骨結節との間にある。
- 鼠径靭帯は鼠径溝の下にある。
- 鼠径靭帯と寛骨との間には筋裂孔がある。
- 鼠径靭帯と寛骨との間には鼠径管がある。
回答はこちらをタップ
4.鼠径靭帯と寛骨との間には鼠径管がある。
問題13 斜角筋隙を通過するのはどれか。
- 鎖骨下動脈
- 腋窩動脈
- 椎骨動脈
- 腕頭動脈
回答はこちらをタップ
1.鎖骨下動脈
問題14 正しいのはどれか。
- 卵巣は中腔性器官である。
- 卵巣は皮質と髄質とからなる。
- 卵胞は髄質にある。
- 卵細胞は黄体内にある。
回答はこちらをタップ
2.卵巣は皮質と髄質とからなる。
問題15 大脳半球の中心溝はどこにあるか。
- 前頭葉と頭頂葉との間
- 頭頂葉と側頭葉との間
- 後頭葉と頭頂葉との間
- 側頭葉と後頭葉との間
回答はこちらをタップ
1.前頭葉と頭頂葉との間
問題16 中胚葉から分化するのはどれか。
- 神経細胞
- 肝細胞
- 骨格筋細胞
- 表皮の上皮細胞
回答はこちらをタップ
3.骨格筋細胞
問題17 椎骨にあるのはどれか。
- 上関節突起
- 茎状突起
- 烏口突起
- 鈎状突起
回答はこちらをタップ
1.上関節突起
問題18 関節半月があるのはどれか。
- 肩関節
- 股関節
- 足関節
- 膝関節
回答はこちらをタップ
4.膝関節
問題19 橈骨手根関節の関節面を構成する組合せはどれか。
- 舟状骨、月状骨、豆状骨
- 月状骨、三角骨、豆状骨
- 舟状骨、月状骨、三角骨
- 舟状骨、三角骨、豆状骨
回答はこちらをタップ
3.舟状骨、月状骨、三角骨
問題20 器官の配列で正しいのはどれか。
- 胃→十二指腸→回腸→空腸
- 鼻腔→喉頭→咽頭→気管
- 腎臓→尿道→膀胱→尿管
- 精巣→精巣上体→精管→尿道
回答はこちらをタップ
4.精巣→精巣上体→精管→尿道
問題21 脈管について誤っているのはどれか。
- 左総頸動脈は大動脈弓から出る。
- 肝静脈は下大静脈に注ぐ。
- 胸管は右の静脈角に注ぐ。
- 肺動脈は右心室から出る。
回答はこちらをタップ
3.胸管は右の静脈角に注ぐ。
問題22 一対の頭蓋骨はどれか。
- 後頭骨
- 下顎骨
- 頭頂骨
- 鋤骨
回答はこちらをタップ
3.頭頂骨
問題23 神経系の伝導路について誤っているのはどれか。
- 錐体路は下行性である。
- 視覚路は下行性である。
- 痛覚路は上行性である。
- 嗅覚路は上行性である。
回答はこちらをタップ
2.視覚路は下行性である。
問題24 腹膜腔に開口しているのはどれか。
- 子宮
- 膣
- 陰核
- 卵管
回答はこちらをタップ
4.卵管
問題25 誤っているのはどれか。
- 真皮は密線維性(強靭)結合組織である。
- 皮下組織は疎線維性結合組織である。
- 大汗腺は全身の皮膚にある。
- 爪は表皮が変形したものである。
回答はこちらをタップ
3.大汗腺は全身の皮膚にある。
問題26 脊髄神経について誤っているのはどれか。
- 頸神経は7対である。
- 胸神経は12対である。
- 腰神経は5対である。
- 仙骨神経は5対である。
回答はこちらをタップ
1.頸神経は7対である。
問題27 消化管について誤っているのはどれか。
- 回腸には集合リンパ小節がある。
- 結腸には輪状ヒダがある。
- 直腸肛門部には静脈叢が多い。
- 胃の大弯には大網がついている。
回答はこちらをタップ
2.結腸には輪状ヒダがある。
問題28 体表から触れるのはどれか。
- 内肋間筋
- 胸鎖乳突筋
- 腹横筋
- 大腰筋
回答はこちらをタップ
2.胸鎖乳突筋
問題29 内分泌腺はどれか。
- 前立腺
- 顎下腺
- 甲状腺
- 大前庭腺
回答はこちらをタップ
3.甲状腺
問題30 細胞のエネルギー産生に関与するのはどれか。
- 中心小体
- ミトコンドリア
- 小胞体
- ゴルジ装置
回答はこちらをタップ
2.ミトコンドリア
問題31 溶血を誘発する因子で誤っているのはどれか。
- 蛇毒
- アシドーシス
- 細胞毒素
- 低張液
回答はこちらをタップ
2.アシドーシス
問題32 血液が運搬しないのはどれか。
- インパルス
- 栄養素
- 血液ガス
- 体熱
回答はこちらをタップ
1.インパルス
問題33 呼吸運動の反射性調節で誤っているのはどれか。
- 血圧上昇による抑制
- 気道粘膜刺激による咳
- 痛み刺激による促進
- 鼻粘膜刺激によるくしゃみ
回答はこちらをタップ
1.血圧上昇による抑制
問題34 誤っている組合せはどれか。
- ビタミンA ─── 上皮組織の角化形成
- ビタミンE ─── 精子の形成
- ビタミンB6 ─── 糖代謝に関与
- ビタミンD ─── Ca2+代謝に関与
回答はこちらをタップ
3.ビタミンB6 ─── 糖代謝に関与
問題35 尿細管で選択的に再吸収されるのはどれか。
- 尿素
- 硫酸塩
- 尿酸
- ブドウ糖
回答はこちらをタップ
4.ブドウ糖
問題36 神経線維の機能について正しい組合せはどれか。
- Aα ─── 触圧覚
- Aβ ─── 自己受容
- Aγ ─── 筋紡錘の感度調節
- Aδ ─── 味覚
回答はこちらをタップ
3.Aγ ─── 筋紡錘の感度調節
問題37 脳波について誤っているのはどれか。
- α波 ─── 閉眼安静時
- β波 ─── 精神活動時
- θ波 ─── 麻酔時
- δ波 ─── 深睡眠時
回答はこちらをタップ
3.θ波 ─── 麻酔時
問題38 副交感神経の自律神経反射で正しいのはどれか。
- 縮瞳
- 心拍数増加
- 乳汁分泌
- 射精
回答はこちらをタップ
1.縮瞳
問題39 細胞内液の代表的陰イオンはどれか。
- 硝酸イオン
- リン酸イオン
- 重炭酸イオン
- 塩素イオン
回答はこちらをタップ
2.リン酸イオン
問題40 赤血球の産生調節に関与するのはどれか。
- エリスロポイエチン
- フィブリノゲン
- トロンボプラスチン
- プラスミノゲン
回答はこちらをタップ
1.エリスロポイエチン
問題41 安静呼息時について正しいのはどれか。
- 横隔膜沈下
- 胸腔内陰圧の増加
- 肋骨挙上
- 胸郭縮小
回答はこちらをタップ
4.胸郭縮小
問題42 精神性発汗が起こらないのはどれか。
- 手掌
- 額
- 腋窩
- 足底
回答はこちらをタップ
2.額
問題43 排便反射の誘発について誤っているのはどれか。
- 結腸の強い蠕動
- 腹圧の上昇
- 骨盤神経求心路の興奮
- 直腸壁の伸展
回答はこちらをタップ
2.腹圧の上昇
問題44 遠位尿細管でのナトリウムイオンの再吸収を促すのはどれか。
- アルドステロン
- バゾプレッシン
- レニン
- アンギオテンシン
回答はこちらをタップ
1.アルドステロン
問題45 視床下部ホルモンによる分泌抑制を受けないのはどれか。
- メラニン細胞刺激ホルモン
- プロラクチン
- 成長ホルモン
- 甲状腺刺激ホルモン
回答はこちらをタップ
4.甲状腺刺激ホルモン
問題46 横紋筋線維について正しいのはどれか。
- 明るい部分をA帯という。
- 暗い部分をI帯という。
- I帯の中央にZ帯がある。
- 収縮すると明るい部分が増加する。
回答はこちらをタップ
3.I帯の中央にZ帯がある。
問題47 ブドウ糖の細胞内代謝について誤っているのはどれか。
- TCAサイクルを経過する。
- 解糖過程は酸素を必要とする。
- 電子伝達系でATPが生成される。
- 1分子のブドウ糖から6分子のCO2が生じる。
回答はこちらをタップ
2.解糖過程は酸素を必要とする。
問題48 血液pHの調節に関与しないのはどれか。
- 肺でのガス交換
- 血漿重炭酸塩
- 腎臓での尿生成
- 肝臓でのビリルビン生成
回答はこちらをタップ
4.肝臓でのビリルビン生成
問題49 体熱の産生に関与しないのはどれか。
- 甲状腺ホルモンの作用
- 褐色脂肪組織の代謝
- 温熱性発汗
- 皮膚血管の収縮
回答はこちらをタップ
3.温熱性発汗
問題50 安静時のクリアランスの値がゼロを示すのはどれか。
- 尿素
- ブドウ糖
- クレアチニン
- アンモニア
回答はこちらをタップ
2.ブドウ糖
問題51 分泌量が視床下部ホルモンの影響を受けないのはどれか。
- プロゲステロン
- テストステロン
- 糖質コルチコイド
- インスリン
回答はこちらをタップ
4.インスリン
問題52 自律神経系の二重支配を受けないのはどれか。
- 唾液腺
- 心臓
- 副腎髄質
- 膀胱
回答はこちらをタップ
3.副腎髄質
問題53 筋収縮エネルギー生成に直接関与するのはどれか。
- アデノシン3リン酸
- クレアチニン
- ピルビン酸
- アセチルCoA
回答はこちらをタップ
1.アデノシン3リン酸
問題54 味覚について誤っているのはどれか。
- 4種類の基本味からなる。
- 酸味は主に舌尖で感じる。
- 順応は著明である。
- 味細胞の寿命は短い。
回答はこちらをタップ
2.酸味は主に舌尖で感じる。
問題55 女性の性周期について誤っているのはどれか。
- 卵巣の黄体期は子宮の分泌期に対応する。
- 排卵は黄体形成ホルモンの急激な増加に伴って起こる。
- 黄体期では血中プロゲステロンが増加する。
- 血中エストロゲンの増加により子宮内膜が脱落する。
回答はこちらをタップ
4.血中エストロゲンの増加により子宮内膜が脱落する
問題56 歩行における立脚期後期に働く筋はどれか。
- 前脛骨筋
- 下腿三頭筋
- 大腿四頭筋
- ハムストリングス
回答はこちらをタップ
2.下腿三頭筋
問題57 正しい組合せはどれか。
- 大殿筋 ─── 上殿神経
- 大腿筋膜張筋 ─── 下殿神経
- 中殿筋 ─── 下殿神経
- 縫工筋 ─── 大腿神経
回答はこちらをタップ
4.縫工筋 ─── 大腿神経
問題58 誤っているのはどれか。
- 筋紡錘の求心性神経線維はⅠa群とⅡ群線維とである。
- 筋の錘内筋線維はγ運動神経の支配を受ける。
- 筋の錘外筋線維はα運動神経の支配を受ける。
- 腱紡錘の求心性神経線維はⅢ群線維である。
回答はこちらをタップ
4.腱紡錘の求心性神経線維はⅢ群線維である。
問題59 良肢位について誤っているのはどれか。
- 肩関節外転60~80度、水平屈曲約30度、外旋約20度
- 肘関節屈曲30度、前腕回内回外中間位
- 手関節10~20度背屈位
- 足関節屈曲(底屈)伸展(背屈)0~10度
回答はこちらをタップ
2.肘関節屈曲30度、前腕回内回外中間位
問題60 神経伝導速度について誤っているのはどれか。
- 温度の影響を受ける。
- 有髄神経より無髄神経の方が速い。
- 新生児では成人の約50%である。
- 神経線維の太さに関係する。
回答はこちらをタップ
2.有髄神経より無髄神経の方が速い。
問題61 肩関節を外旋する働きのあるのはどれか。
- 大胸筋
- 大円筋
- 肩甲下筋
- 小円筋
回答はこちらをタップ
4.小円筋
問題62 二重神経支配の筋と神経との組合せで誤っているのはどれか。
- 恥骨筋 ─── 閉鎖神経、坐骨神経
- 腸腰筋 ─── 腰神経叢、大腿神経
- 大腿二頭筋 ─── 脛骨神経、総腓骨神経
- 大内転筋 ─── 閉鎖神経、坐骨神経
回答はこちらをタップ
1.恥骨筋 ─── 閉鎖神経、坐骨神経
問題63 筋収縮様式で効率のよいのはどれか。
- 遠心性収縮
- 等尺性収縮
- 求心性収縮
- 等張性収縮
回答はこちらをタップ
2.等尺性収縮
問題64 走行が歩行と異なる点について正しいのはどれか。
- 床面との摩擦が少ない。
- 減速要素が多い。
- 身体の前傾角度が少ない。
- 両脚支持期がない。
回答はこちらをタップ
4.両脚支持期がない。
問題65 重心を規定する要素で誤っているのはどれか。
- 基本矢状面、基本前額面、基本水平面の3つの面が交差する点
- 身体各部の重量が相互に平衡である点
- 頭部、体幹、四肢の各分節の中心を通る点
- 身体があらゆる方向に自由に回転し得る点
回答はこちらをタップ
3.頭部、体幹、四肢の各分節の中心を通る点
問題66 免疫について誤っているのはどれか。
- 免疫応答には特異性がある。
- 初めに自己と非自己との識別がなされる。
- 免疫グロブリンはリンパ球T細胞でつくられる。
- 細胞性免疫はリンパ球T細胞が関与する。
回答はこちらをタップ
3.免疫グロブリンはリンパ球T細胞でつくられる
問題67 自覚症状でないのはどれか。
- 白血球増多
- 倦怠
- 悪心
- 熱感
回答はこちらをタップ
1.白血球増多
問題68 誤っている組合せはどれか。
- 痛風 ─── 高尿酸血症
- 閉塞性黄疸 ─── 間接ビリルビン上昇
- ヘモクロマトーシス ─── ヘモジデリン沈着
- 褐色萎縮 ─── リポフスチン沈着
回答はこちらをタップ
2.閉塞性黄疸 ─── 間接ビリルビン上昇
問題69 感染経路と疾患との組合せで誤っているのはどれか。
- 経口感染 ─── 腸チフス
- 経皮感染 ─── 日本脳炎
- 経胎盤感染 ─── 先天梅毒
- 経気道感染 ─── 赤痢
回答はこちらをタップ
4.経気道感染 ─── 赤痢
問題70 腫瘍について誤っているのはどれか。
- 上皮性悪性腫瘍 ─── 印環細胞癌
- 上皮性良性腫瘍 ─── 移行上皮癌
- 非上皮性悪性腫瘍 ─── 白血病
- 非上皮性良性腫瘍 ─── 神経鞘腫
回答はこちらをタップ
2.上皮性良性腫瘍 ─── 移行上皮癌
問題71 悪性腫瘍の特徴について誤っているのはどれか。
- 転移
- 圧排性発育
- 浸潤性増殖
- 播種
回答はこちらをタップ
2.圧排性発育
問題72 自己免疫疾患でないのはどれか。
- 全身性エリテマトーデス
- 橋本病
- 気管支喘息
- 皮膚筋炎
回答はこちらをタップ
3.気管支喘息
問題73 アレルギーについて誤っているのはどれか。
- アナフィラキシー型(Ⅰ型) ─── 蕁麻疹
- 細胞障害型(Ⅱ型) ─── 溶血性貧血
- 免疫複合体型(Ⅲ型) ─── 血清病
- 細胞免疫型(Ⅳ型) ─── 花粉症
回答はこちらをタップ
4.細胞免疫型(Ⅳ型) ─── 花粉症
問題74 正しい組合せはどれか。
- HTLウイルス ─── 慢性骨髄性白血病
- HBウイルス ─── 肝細胞癌
- EBウイルス ─── 肺癌
- パピローマウイルス ─── 大腸癌
回答はこちらをタップ
2.HBウイルス ─── 肝細胞癌
問題75 病原体と疾患との組合せで誤っているのはどれか。
- ウイルス ─── コレラ
- 真菌 ─── カンジダ症
- リケッチア ─── ツツガムシ病
- 原虫 ─── アメーバ赤痢
回答はこちらをタップ
1ウイルス ─── コレラ
問題76 炎症について誤っている組合せはどれか。
- 細菌感染 ─── 細胞壊死
- 炎症性浮腫 ─── 低蛋白血症
- 化膿 ─── 好中球の浸潤
- 炎症性肉芽 ─── 線維芽細胞の増生
回答はこちらをタップ
2.炎症性浮腫 ─── 低蛋白血症
問題77 結核症でみられないのはどれか。
- 凝固壊死
- 血行性蔓延
- 脊椎カリエス
- カタル性炎
回答はこちらをタップ
4.カタル性炎
問題78 梗塞が原因となるのはどれか。
- 水頭症
- 脳軟化症
- 狭心症
- 水腎症
回答はこちらをタップ
2.脳軟化症
問題79 プライマリ・ケアを採択しているのはどれか。
- WHO憲章
- オタワ憲章
- アルマ・アタ宣言
- ヘルシンキ宣言
回答はこちらをタップ
3.アルマ・アタ宣言
問題80 大気汚染物質でないのはどれか。
- NOχ(窒素酸化物)
- SPM(浮遊粒子状物質)
- SOχ(硫黄酸化物)
- PCB(塩素化ビフェニル)
回答はこちらをタップ
4.PCB(塩素化ビフェニル)
問題81 水道法で規定する水質基準はどれか。
- BOD(生物的酸素要求量)
- COD(化学的酸素要求量)
- pH(水素イオン濃度)
- DO(溶存酸素)
回答はこちらをタップ
3.pH(水素イオン濃度)
問題82 室内の不快指数を測定する器具はどれか。
- アスマン通風乾湿湿度計
- カタ寒暖計
- 黒球温度計
- 自記温度計
回答はこちらをタップ
1.アスマン通風乾湿湿度計
問題83 器具の消毒に使われないのはどれか。
- 紫外線
- 赤外線
- 乾熱
- 煮沸
回答はこちらをタップ
2.赤外線
問題84 検疫伝染病でないのはどれか。※解なし
- 黄熱
- コレラ
- 痘瘡
- ラッサ熱
回答はこちらをタップ
問題85 誤っている組合せはどれか。
- ジフテリア ─── 桿菌
- トキソプラズマ ─── 真菌
- 日本脳炎 ─── ウイルス
- オウム病 ─── クラミジア
回答はこちらをタップ
2.トキソプラズマ ─── 真菌
問題86 エイズ感染について誤っているのはどれか。
- 性交感染
- 血液感染
- 飛沫感染
- 母子感染
回答はこちらをタップ
3.飛沫感染
問題87 保健所の業務で誤っているのはどれか。
- 精神障害者の保健の向上
- 地域の保健統計
- 産業保健
- 歯科保健
回答はこちらをタップ
3.産業保健
問題88 業務上疾病件数で最も多いのはどれか。
- じん肺及びじん肺合併症
- 負傷に起因する疾病
- 暑熱、寒冷等物理的因子による疾病
- 有機溶剤等化学物質による疾病
回答はこちらをタップ
2.負傷に起因する疾病
問題89 食中毒の原因となるのはどれか。
- エンテロウイルス
- リケッチア
- 腸炎ビブリオ
- スピロヘータ
回答はこちらをタップ
3.腸炎ビブリオ
問題90 疾病と危険因子との組合せで誤っているのはどれか。
- 脳血管疾患 ─── 過激な労働
- がん ─── カルシウムの不足
- 心疾患 ─── 喫煙量の増加
- 高血圧 ─── 塩分摂取量の増加
回答はこちらをタップ
2.がん ─── カルシウムの不足
問題91 柔道整復師免許について正しいのはどれか。
- 免許証明書を紛失した場合でも柔道整復の業務を行うことができる。
- 取り消されると再免許は与えられない。
- 外国籍となった場合は取り消される。
- 一定期間ごとに更新する必要がある。
回答はこちらをタップ
1.免許証明書を紛失した場合でも柔道整復の業務を行うことができる。
問題92 柔道整復師名簿訂正の申請を必要とするのはどれか。
a.本籍地の都道府県名に変更があったとき。
b.結婚して改姓したとき。
c.業務の停止処分を受けたとき。
d.住所に変更があったとき。
- a、b
- a、d
- b、c
- c、d
回答はこちらをタップ
1.a、b
問題93 免許を取り消されたとき免許証明書の返納期間で正しいのはどれか。
- 直ちに
- 5日以内
- 10日以内
- 30日以内
回答はこちらをタップ
2.5日以内
問題94 柔道整復師の施術として正しいのはどれか。
a.医師の同意を得ないで大腿骨骨折の患部に応急手当をした。
b.歯科医師の同意を得て下顎骨骨折の患部に施術した。
c.医師の同意を得て上腕骨骨折の患部のエックス線撮影をした。
d.医師の同意を得ないで足関節捻挫の患部に施術した。
- a、b
- a、d
- b、c
- c、d
回答はこちらをタップ
2.a、d
問題95 柔道整復師が施術にあたり必要な医師の同意について正しいのはどれか。
- 整形外科の医師に限らない。
- 医師が直接患者を診察する必要はない。
- 同意書が必要である。
- 施術者が直接医師から得なければならない。
回答はこちらをタップ
1.整形外科の医師に限らない。
問題96 施術所の名称として使用することができるのはどれか。
- ○○接骨医院
- ○○柔道整復科療院
- ほねつぎ院
- ○○整骨クリニック
回答はこちらをタップ
3.ほねつぎ院
問題97 施術所について誤っているのはどれか。
- 施術室の専用面積は6.6m2以上でなければならない。
- 施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有しなければならない。
- 保健所を設置する市に所在する場合は市長が業務を監督する。
- 休止する場合は都道府県知事の許可を受けなければならない。
回答はこちらをタップ
4.休止する場合は都道府県知事の許可を受けなければならない。
問題98 保健所を設置する市の市長が行った施術所の構造設備の改善命令の処分について、不服のある場合、審査請求先はどれか。
- 保健所長
- 市長
- 都道府県知事
- 厚生大臣
回答はこちらをタップ
3.都道府県知事
問題99 免許資格が業務独占でないのはどれか。
- 看護婦(士)
- 柔道整復師
- 衛生検査技師
- 診療放射線技師
回答はこちらをタップ
3.衛生検査技師
問題100 正しいのはどれか。
- 病院は患者20人以上の収容施設を有する。
- 診療所には患者の収容施設はない。
- 特定機能病院は特定の患者のみを診察する。
- 総合病院には全ての診療科を置かなければならない。
回答はこちらをタップ
1.病院は患者20人以上の収容施設を有する。
【午後問題】第4回柔道整復師国家試験
問題101 糖尿病の問診項目として適切でないのはどれか。
- 睡眠
- 体重
- 食事
- 運動
回答はこちらをタップ
1.睡眠
問題102 視診について誤っているのはどれか。
- 脊柱後弯姿勢 ─── 脊椎カリエス
- マン・ウェルニッケ姿勢 ─── 重症筋無力症
- 前かがみの姿勢 ─── パーキンソン病
- エビ姿勢 ─── 胆石症
回答はこちらをタップ
2.マン・ウェルニッケ姿勢 ─── 重症筋無力症
問題103 正しい組合せはどれか。
- 分回し歩行 ─── 脳性小児麻痺
- はさみ状歩行 ─── バージャー病
- アヒル歩行 ─── 前脛骨筋麻痺
- 突進歩行 ─── パーキンソン病
回答はこちらをタップ
4.突進歩行 ─── パーキンソン病
問題104 痛みを伴うリンパ節腫大はどれか。
- 化膿性リンパ節炎
- 結核性リンパ節炎
- 悪性リンパ腫
- 癌のリンパ節転移
回答はこちらをタップ
1.化膿性リンパ節炎
問題105 触診方法で正しいのはどれか。
- 訴える部位から触診する。
- ボアス点の判定は背臥位で行う。
- 腎臓は側腹部前後を両手で挟む。
- 筋萎縮は力を抜いた筋肉の硬さをみる。
回答はこちらをタップ
3.腎臓は側腹部前後を両手で挟む。
問題106 体温について正しい組合せはどれか。
a.バセドウ病 ─── 微熱
b.敗血症 ─── 弛張熱
c.マラリア ─── 稽留熱
d.膠原病 ─── 周期的発熱
- a、b
- a、d
- b、c
- c、d
回答はこちらをタップ
1.a、b
問題107 速脈がみられないのはどれか。
- 大動脈弁閉鎖不全症
- 僧帽弁狭窄症
- 貧血
- 甲状腺機能亢進症
回答はこちらをタップ
2.僧帽弁狭窄症
問題108 上肢の病的反射はどれか。
a.ゴルドン反射 b.ホフマン反射 c.トレムナー反射 d.シェーファー反射
- a、b
- a、d
- b、c
- c、d
回答はこちらをタップ
3.b、c
問題109 正しい組合せはどれか。
- 橈骨神経麻痺 ─── 下垂手
- 尺骨神経麻痺 ─── 猿手
- 正中神経麻痺 ─── 鷲手
- 脛骨神経麻痺 ─── 尖足
回答はこちらをタップ
1.橈骨神経麻痺 ─── 下垂手
問題110 上位運動ニューロン障害でみられないのはどれか。
- 病的反射の出現
- 深部腱反射の亢進
- 神経原性萎縮
- 痙性麻痺
回答はこちらをタップ
2.深部腱反射の亢進
問題111 ギラン・バレー症候群にみられないのはどれか。
- 両側顔面麻痺
- 呼吸障害
- 四肢鉛管現象
- 構音障害
回答はこちらをタップ
3.四肢鉛管現象
問題112 正しい組合せはどれか。
1.消化性潰瘍 ─── 下部消化管の潰瘍
2.腸閉塞 ─── 腸内容の通過障害
3.肝硬変 ─── 肝臓の悪性腫瘍
4.急性膵炎 ─── 膵臓の細菌感染
回答はこちらをタップ
2.腸閉塞 ─── 腸内容の通過障害
問題113 消化器症状について誤っている組合せはどれか。
- 胸やけ ─── 食道癌
- 心窩部痛 ─── 胃癌
- 粘血便 ─── 大腸癌
- 右上腹部痛 ─── 胆石症
回答はこちらをタップ
1.胸やけ ─── 食道癌
問題114 腹膜炎でみられないのはどれか。
- 筋性防御
- 圧痛
- 反動痛
- 腸蠕動音亢進
回答はこちらをタップ
4.腸蠕動音亢進
問題115 鉄欠乏性貧血について誤っているのはどれか。
- 血清鉄値は低下する。
- 高色素性貧血となる。
- 子宮筋腫は一因となる。
- さじ状爪となる。
回答はこちらをタップ
2.高色素性貧血となる。
問題116 慢性関節リウマチについて正しいのはどれか。
- 手指関節炎はまれである。
- 皮下結節を触れる。
- 発作性の関節炎が多い。
- 小児にはみられない。
回答はこちらをタップ
2.皮下結節を触れる
問題117 誤っている組合せはどれか。
- アジソン病 ─── 色素沈着
- 褐色細胞腫 ─── 高血圧
- クッシング症候群 ─── 体重減少
- 粘液水腫 ─── 徐脈
回答はこちらをタップ
3.クッシング症候群 ─── 体重減少
問題118 ネフローゼ症候群で低下するのはどれか。
- 血清アルブミン
- 血清コレステロール
- 血清トリグリセリド
- 尿中蛋白量
回答はこちらをタップ
1.血清アルブミン
問題119 心不全について正しいのはどれか。
a.左心不全では起坐呼吸がみられる。
b.右心不全では静脈圧が低下する。
c.心タンポナーデでは収縮不全がみられる。
d.高血圧性心不全は機械的障害による。
- a、b
- a、d
- b、c
- c、d
回答はこちらをタップ
2.a、d
問題120 虚血性心疾患について誤っているのはどれか。
- 狭心症発作は一過性の心筋虚血で生じる。
- 狭心症発作の持続は数分である。
- 急性心筋梗塞では血清CKが増加する。
- 冠危険因子には血清コレステロールの低下がある。
回答はこちらをタップ
4.冠危険因子には血清コレステロールの低下がある。
問題121 消毒・滅菌法について誤っているのはどれか。
- ヨードホルム消毒法 ─── 手指・創傷
- 煮沸滅菌法 ─── 手術野・熱傷
- ガス滅菌法 ─── 光学レンズ・ゴム製品
- 高圧蒸気滅菌法 ─── 手術器具・ガーゼ
回答はこちらをタップ
2.煮沸滅菌法 ─── 手術野・熱傷
問題122 局所麻酔法でないのはどれか。
- 脊椎麻酔
- 硬膜外麻酔
- 浸潤麻酔
- 静脈麻酔
回答はこちらをタップ
4.静脈麻酔
問題123 止血法について誤っているのはどれか。
- 出血部位を直接圧迫するのを結紮法という。
- 駆血帯などで止血するのを緊縛法という。
- ガーゼなどをつめて止血するのを圧迫タンポン法という。
- 内視鏡などを用いて塞栓・硬化させるのを血管内塞栓法という。
回答はこちらをタップ
1.出血部位を直接圧迫するのを結紮法という。
問題124 ショックについて正しいのはどれか.
- 循環血流量の増加が原因である。
- 細菌感染も原因となる。
- 出血性ショックは不可逆的である。
- 心原性ショックは一過性である。
回答はこちらをタップ
2.細菌感染も原因となる。
問題125 創傷について正しいのはどれか.
- 微小血管損傷は自然止血しない。
- 損傷部が腫脹するのは血液成分の漏出による。
- リンパ球は壊死組織を分解吸収する。
- 白血球は瘢痕組織の一部である。
回答はこちらをタップ
2.損傷部が腫脹するのは血液成分の漏出による
問題126 外科的感染症と原因菌との組合せで誤っているのはどれか。
- 破傷風 ─── 嫌気性菌
- 蜂窩織炎 ─── 結核菌
- 癰(セツ) ─── ブドウ球菌
- 丹毒 ─── 溶血性連鎖球菌
回答はこちらをタップ
2.蜂窩織炎 ─── 結核菌
問題127 頭部外傷について正しいのはどれか。
- 巣症状が認められる場合は脳挫傷が疑われる。
- 耳出血がある場合は後頭骨骨折が疑われる。
- 受傷部の腫脹は硬膜外血腫による。
- 開口障害は頭蓋底骨折が原因である。
回答はこちらをタップ
1.巣症状が認められる場合は脳挫傷が疑われる。
問題128 正しい組合せはどれか。
- 植物状態 ─── 大脳障害
- 脳死 ─── 脊髄損傷
- 痙攣 ─── 慢性関節リウマチ
- 片頭痛 ─── 頭頸部筋持続的収縮
回答はこちらをタップ
1.植物状態 ─── 大脳障害
問題129 交通外傷による腹部鈍的損傷で正しいのはどれか。
- ハンドルによる上腹部打撲で消化管損傷が生じる。
- 肋骨骨折を伴う場合には膵損傷が多い。
- シートベルトによる皮膚圧痕は特に処置を要しない。
- 前腹壁打撲により腎損傷が生じる。
回答はこちらをタップ
1.ハンドルによる上腹部打撲で消化管損傷が生じる。
問題130 胸・腹部複合型外傷で優先して行う処置はどれか。
a.気道確保 b.血管確保 c.創部清浄化 d.骨折部処置
- a、b
- a、d
- b、c
- c、d
回答はこちらをタップ
1.a、b
問題131 分裂膝蓋骨について正しいのはどれか。
- 女性に多い。
- 無症状のものが多い。
- 骨折後の偽関節である。
- 膝蓋骨が4つ以上に分裂する。
回答はこちらをタップ
2.無症状のものが多い。
問題132 神経病性関節症の原因疾患について誤っているのはどれか。
- 脊髄空洞化
- 糖尿病
- 脊髄癆
- 痛風
回答はこちらをタップ
4.痛風
問題133 神経根引き抜き損傷について正しいのはどれか。
a.牽引損傷である。 b.軸索反射は陽性である。 c.脊髄造影像では異常を認めない。 d.予後は良好である。
- a、b
- a、d
- b、c
- c、d
回答はこちらをタップ
1.a、b
問題134 関節液の性状について誤っているのはどれか。
- 変形性関節症では混濁している。
- 痛風発作時は針状結晶を認める。
- 関節内骨折では脂肪滴を認める。
- 前十字靭帯損傷では血性となる。
回答はこちらをタップ
1.変形性関節症では混濁している。
問題135 二次性骨粗鬆症として誤っているのはどれか。
- 妊娠後骨粗鬆症
- 末端肥大症に伴う骨粗鬆症
- 甲状腺機能亢進症に伴う骨粗鬆症
- 廃用性骨粗鬆症
回答はこちらをタップ
1.妊娠後骨粗鬆症
問題136 正しいのはどれか。
- デュピュートレン拘縮は狭窄性腱鞘炎である。
- ヘバーデン結節はPIP関節の変形性関節症である。
- ド・ケルバン病は手関節の変形性関節症である。
- マレットフィンガーには骨折または腱断裂がある。
回答はこちらをタップ
4.マレットフィンガーには骨折または腱断裂がある。
問題137 40~60歳に好発する腫瘍はどれか。
- 骨肉腫
- 多発性骨髄腫
- ユーイング肉腫
- 神経芽細胞腫
回答はこちらをタップ
2.多発性骨髄腫
問題138 無腐性骨壊死の発生部位について正しい組合せはどれか。
- オスグッド病 ─── 大腿骨
- キーンベック病 ─── 月状骨
- ショイエルマン病 ─── 上腕骨
- ペルテス病 ─── 足舟状骨
回答はこちらをタップ
2.キーンベック病 ─── 月状骨
問題139 手根管症候群について誤っているのはどれか。
- 女性に多い。
- 腎透析の患者にみられる。
- 小指球筋萎縮が起こる。
- 神経伝導テストに遅延がみられる。
回答はこちらをタップ
3.小指球筋萎縮が起こる。
問題140 腱板について誤っているのはどれか。
- 肩甲下筋、棘上筋、棘下筋、小円筋から成る。
- 損傷は中年の男性に多い。
- 棘下筋腱が最も損傷されやすい。
- 損傷の確定診断には関節造影を行う。
回答はこちらをタップ
3.棘下筋腱が最も損傷されやすい
問題141 国際的障害分類と解決方法との組合せで誤っているのはどれか。
- 機能形態障害 ─── 関節可動域訓練
- 能力低下 ─── 日常生活動作訓練
- 社会的不利 ─── 車椅子の使用
- 社会的不利 ─── 公共交通機関の整備
回答はこちらをタップ
3.社会的不利 ─── 車椅子の使用
問題142 運動方向について誤っている組合せはどれか。
a.肩関節伸展 ─── 上腕を矢状面内で後方に動かす。
b.母指掌側外転 ─── 母指を手掌と直角の方向に動かす。
c.股関節外転 ─── 下肢を長軸に沿って外側にひねる。
d.足関節背屈 ─── 足部を足底の方向に動かす。
- a、b
- a、d
- b、c
- c、d
回答はこちらをタップ
4.c、d
問題143 徒手筋力テストについて誤っている組合せはどれか。
a.Normal(筋力5) ─── 強い抵抗に逆らって全可動域を動かせる。
b.Good(筋力4) ─── 抵抗に逆らって可動域の一部を動かせる。
c.Fair(筋力3) ─── 重力の影響を取り除くと全可動域を動かせる。
d.Trace(筋力1) ─── 筋の収縮を確認できるが関節を動かせない。
- a、b
- a、d
- b、c
- c、d
回答はこちらをタップ
3.b、c
問題144 漸増的筋力強化法で正しいのはどれか。
- ボイタ法
- ブルンストローム法
- ボバース法
- デュローム法
回答はこちらをタップ
4.デュローム法
問題145 物理療法で正しいのはどれか。
- 超音波は体内金属がある時には使用できない。
- ホットパックは心臓ペースメーカー使用者には使用できない。
- 赤外線は椎弓切除部には使用できない。
- 極超短波は感覚脱失部には使用できない。
回答はこちらをタップ
4.極超短波は感覚脱失部には使用できない。
問題146 下肢装具の主要目的で誤っているのはどれか。
- 体重支持
- 固定
- 喪失部位の補てん
- 変形予防
回答はこちらをタップ
3.喪失部位の補てん
問題147 脳卒中で誤っているのはどれか。
- 老人では脳出血が脳梗塞より多い。
- 糖尿病は危険因子の一つである。
- 発症直後では弛緩性麻痺となる。
- 膝関節の伸展位変形拘縮を起こしやすい。
回答はこちらをタップ
1.老人では脳出血が脳梗塞より多い
問題148 片麻痺の能力障害に対する治療で正しいのはどれか。
- 利き手交換
- 筋持久力改善
- 運動麻痺改善
- 関節可動域改善
回答はこちらをタップ
1.利き手交換
問題149 脳性麻痺で正しいのはどれか。
- 進行性である。
- 筋肉に仮性肥大がある。
- 痙直型が多い。
- 精神機能低下がある。
回答はこちらをタップ
3.痙直型が多い
問題150 五十肩の急性期治療で適切でないのはどれか。
- コッドマン体操
- 他動的外旋運動
- 温熱療法
- 自動介助運動
回答はこちらをタップ
2.他動的外旋運動
問題151 末梢神経損傷について正しいのはどれか。
a.ワーラー変性は末梢神経の変性である。
b.神経の再生速度は一日平均1~4mmである。
c.麻痺域の皮膚電気抵抗は減少する。
d.チネル徴候の進行停止は神経の再生を示す。
- a、b
- a、d
- b、c
- c、d
回答はこちらをタップ
1.a、b
問題152 正しいのはどれか。
- 偽関節は骨癒合機転を失ったものをいう。
- 過剰仮骨ができるのは血腫が少ない場合に多い。
- 骨化性筋炎は骨組織の筋化現象である。
- 骨折後の拘縮は骨癒合とともに回復する。
回答はこちらをタップ
1.偽関節は骨癒合機転を失ったものをいう。
問題153 正しい組合せはどれか。
a.裂離骨折 ─── 大腿骨骨幹部
b.螺旋骨折 ─── 尺骨肘頭部
c.圧迫骨折 ─── 腰椎椎体部
d.斜骨折 ─── 上腕骨骨幹部
- a、b
- a、d
- b、c
- c、d
回答はこちらをタップ
4.c、d
問題154 青年のスポーツ外傷で誤っている組合せはどれか。
- 頸椎骨折 ─── ラグビー
- 上腕骨骨折 ─── ベースボール
- 中手骨骨折 ─── ボクシング
- 大腿骨頸部骨折 ─── マラソン
回答はこちらをタップ
4.大腿骨頸部骨折 ─── マラソン
問題155 軋轢音が感知できる骨折はどれか。
- 胸椎圧迫骨折
- 鎖骨若木骨折
- 腸骨亀裂骨折
- 大腿骨頸部骨折
回答はこちらをタップ
4.大腿骨頸部骨折
問題156 骨折の合併症で誤っているのはどれか。
- 上腕骨骨幹部骨折では筋皮神経麻痺が多い。
- 頭蓋骨骨折では頭蓋内出血を伴う。
- 開放性骨折では細菌感染の危険が生じる。
- 多発骨折では脂肪塞栓の危険が生じる。
回答はこちらをタップ
1.上腕骨骨幹部骨折では筋皮神経麻痺が多い。
問題157 関節包外脱臼はどれか。
- 先天性脱臼
- 随意性脱臼
- 病的脱臼
- 外傷性脱臼
回答はこちらをタップ
4.外傷性脱臼
問題158 鎖骨骨折について誤っているのはどれか。
- 腋窩神経損傷を伴う。
- 介達外力で発生しやすい。
- 中・外1/3部の中枢骨片は後上方に転位する。
- 整復の繰り返しは偽関節発生の要因となる。
回答はこちらをタップ
1.腋窩神経損傷を伴う。
問題159 上腕骨上端部骨折について正しいのはどれか。
- 骨頭骨折は骨性癒合が良好である。
- 解剖頸骨折は青壮年者に多発する。
- 骨端離開はソルターハリスのⅠ型が多い。
- 外科頸骨折は介達外力によることが多い。
回答はこちらをタップ
4.外科頸骨折は介達外力によることが多い。
問題160 上腕骨外科頸骨折について正しいのはどれか。
- 内転骨折が多い。
- 関節包内骨折である。
- 内転骨折の末梢骨片は内上方に転位する。
- 合併症として三角筋麻痺がある。
回答はこちらをタップ
4.合併症として三角筋麻痺がある。
問題161 上腕骨骨折について誤っているのはどれか。
- 転位の著しい大結節単独骨折は肩関節外転・外旋位で固定する。
- 小結節単独骨折では上腕三頭筋腱脱臼を起こす。
- 骨幹部骨折では捻転転位を最初に整復する。
- 骨幹部の横骨折は偽関節形成の原因となる。
回答はこちらをタップ
2.小結節単独骨折では上腕三頭筋腱脱臼を起こす。
問題162 上腕骨骨幹部骨折の転位について正しい組合せはどれか。2つ選べ。
- 三角筋付着部より上部骨折 ─── 中枢骨片は内上方転位
- 三角筋付着部より上部骨折 ─── 末梢骨片は外上方転位
- 三角筋付着部より下部骨折 ─── 中枢骨片は外上方転位
- 三角筋付着部より下部骨折 ─── 末梢骨片は前上方転位
回答はこちらをタップ
2.三角筋付着部より上部骨折 ─── 末梢骨片は外上方転位
3.三角筋付着部より下部骨折 ─── 中枢骨片は外上方転位
問題163 上腕骨顆上骨折について正しいのはどれか。
- 阻血性拘縮は6~7日で出現する。
- 伸展骨折の骨折線は前上方から後下方に走行する。
- 屈曲骨折は肘関節後方脱臼と誤診されやすい。
- 伸展骨折の固定肢位は90~110度屈曲する。
回答はこちらをタップ
4.伸展骨折の固定肢位は90~110度屈曲する。
問題164 上腕骨顆部骨折について正しいのはどれか。
- 内上顆骨折は外反が強制され発生する。
- 内上顆骨折の骨片は前上方へ転位する。
- 外顆骨折は遅発性橈骨神経麻痺を起こす。
- 外顆骨折の骨片は前内方へ転位する。
回答はこちらをタップ
1.内上顆骨折は外反が強制され発生する。
問題165 両前腕骨骨幹部骨折について誤っているのはどれか。
- 直達外力では両骨同高位の骨折が多い。
- 小児では不全骨折が多い。
- 定型的転位は骨折部と腕橈骨筋付着部との位置関係による。
- 両骨間に橋状仮骨が形成されると前腕の回旋障害をきたす。
回答はこちらをタップ
3.定型的転位は骨折部と腕橈骨筋付着部との位置関係による。
問題166 延長転位を呈する骨折はどれか。
- 尺骨骨幹上・中1/3境界部での骨折
- 円回内筋付着部より中枢での橈骨骨幹部骨折
- 橈骨骨幹中・下1/3境界部での骨折
- 上腕二頭筋付着部より末梢での肘頭骨折
回答はこちらをタップ
4.上腕二頭筋付着部より末梢での肘頭骨折
問題167 コーレス骨折と同様の機序で発生する骨折はどれか。
- スミス骨折
- ショーファー骨折
- 背側バートン骨折
- パレ骨折
回答はこちらをタップ
3.背側バートン骨折
問題168 橈骨上端部骨折について正しいのはどれか。
- 介達外力による発生頻度が高い。
- 成人では頭部より頸部に発生頻度が高い。
- 関節血腫はみられない。
- 小児でも応変則は期待できない。
回答はこちらをタップ
1.介達外力による発生頻度が高い。
問題169 モンテギア骨折について正しいのはどれか。
- 伸展型は橈骨頭が後外方に脱臼する。
- 屈曲型は伸展型に比較して整復・固定が困難である。
- 伸展型は肘関節伸展位、前腕回外位で固定する。
- 合併症として橈骨神経麻痺がある。
回答はこちらをタップ
4.合併症として橈骨神経麻痺がある
問題170 スミス骨折の末梢骨片転位について正しいのはどれか。
- 掌側・短縮・尺側転位
- 掌側・短縮・橈側転位
- 背側・延長・橈側転位
- 背側・短縮・尺側転位
回答はこちらをタップ
2.掌側・短縮・橈側転位
問題171 手舟状骨骨折が難治である理由について誤っているのはどれか。
- 手関節運動時骨折部に剪力が働く。
- 関節内骨折である。
- 骨折端間に伸筋腱が介在する。
- 近位骨片への血液供給が絶たれる。
回答はこちらをタップ
3.骨折端間に伸筋腱が介在する。
問題172 手指の中節骨骨幹部骨折の転位について正しい組合せはどれか。2つ選べ。
- 浅指屈筋腱付着部より近位骨折 ─── 末梢骨片は背側転位
- 浅指屈筋腱付着部より遠位骨折 ─── 末梢骨片は掌側転位
- 浅指屈筋腱付着部より近位骨折 ─── 中枢骨片は背側転位
- 浅指屈筋腱付着部より遠位骨折 ─── 中枢骨片は掌側転位
回答はこちらをタップ
3.浅指屈筋腱付着部より近位骨折 ─── 中枢骨片は背側転位
4.浅指屈筋腱付着部より遠位骨折 ─── 中枢骨片は掌側転位
問題173 手部の骨折で掌側凸変形となるのはどれか。
- ベンネット骨折
- 中手骨骨幹部骨折
- 基節骨骨幹部骨折
- 中手骨頸部骨折
回答はこちらをタップ
3.基節骨骨幹部骨折
問題174 上前腸骨棘単独骨折の発症に関与しないのはどれか。
a.大腿二頭筋 b.大腿直筋 c.縫工筋 d.大腿筋膜張筋
- a、b
- a、d
- b、c
- c、d
回答はこちらをタップ
1.a、b
問題175 下腿骨上端部骨折と原因との組合せで誤っているのはどれか。
- 脛骨顆部骨折 ─── 垂直の圧挫外力
- 脛骨結節骨折 ─── 大腿四頭筋の牽引
- 脛骨顆間隆起骨折 ─── 脛骨回旋強制
- 腓骨頭単独骨折 ─── 膝関節の過伸展
回答はこちらをタップ
4.腓骨頭単独骨折 ─── 膝関節の過伸展
問題176 下腿骨骨幹部骨折で誤っている組合せはどれか。
- 変形治癒 ─── 反張下腿
- 関節拘縮 ─── 尖足位
- 遷延治癒 ─── 中・下1/3境界部
- 筋萎縮 ─── 早期荷重
回答はこちらをタップ
4.筋萎縮 ─── 早期荷重
問題177 下腿骨果部外転骨折で誤っているのはどれか。
- 外転強制で発生する。
- 足関節外側の靭帯が断裂する。
- 内果の裂離骨折を生じる。
- 外果の上方で骨折を生じる。
回答はこちらをタップ
2.足関節外側の靭帯が断裂する
問題178 踵骨骨折の治療で誤っているのはどれか。
- 足部疼痛の軽減 ─── 温熱療法
- 足底部筋の機能低下防止 ─── 足指の屈伸運動
- 骨萎縮の防止 ─── 長期固定
- 足部慢性浮腫の防止 ─── 足部高挙
回答はこちらをタップ
3.骨萎縮の防止 ─── 長期固定
問題179 脱臼と神経損傷との組合せで誤っているのはどれか。
- 肩関節前方脱臼 ─── 腋窩神経
- 肘関節後方脱臼 ─── 橈骨神経
- 股関節前方脱臼 ─── 坐骨神経
- 膝関節前方脱臼 ─── 脛骨神経
回答はこちらをタップ
3.股関節前方脱臼 ─── 坐骨神経
問題180 脱臼と骨折とが合併しないのはどれか。
- ポット骨折
- ベンネット骨折
- モンテギア骨折
- ジョーンズ骨折
回答はこちらをタップ
4.ジョーンズ骨折
問題181 顎関節脱臼で最も多いのはどれか。
- 前方脱臼
- 後方脱臼
- 側方脱臼
- 中心性脱臼
回答はこちらをタップ
1.前方脱臼
問題182 肩鎖関節脱臼について誤っているのはどれか。
- 男子に多い。
- 反跳症状がみられる。
- 烏口鎖骨靭帯の断裂は第Ⅰ型である。
- 鎖骨外端骨折との鑑別を要する。
回答はこちらをタップ
3.烏口鎖骨靭帯の断裂は第Ⅰ型である。
問題183 肩関節烏口下脱臼について正しいのはどれか。2つ選べ。
- 肩峰下に骨頭が触知できる。
- 上肢長は仮性延長する。
- 鎖骨下脱臼より上腕の外転度が大きい。
- 三角筋麻痺が起これば上腕外転が不能となる。
回答はこちらをタップ
2.上肢長は仮性延長する。
4.三角筋麻痺が起これば上腕外転が不能となる
問題184 肩関節下方脱臼の分類で正しいのはどれか。
a.腋窩脱臼 b.肩峰下脱臼 c.棘下脱臼 d.関節窩脱臼
- a、b
- a、d
- b、c
- c、d
回答はこちらをタップ
2.a、d
問題185 肘内障について誤っているのはどれか。
- 5歳児以下に多発する。
- 前腕回外運動が制限される。
- 肘関節部の腫脹が著名である。
- 橈骨頭部に圧痛がみられる。
回答はこちらをタップ
3.肘関節部の腫脹が著名である
問題186 手関節部の脱臼について誤っているのはどれか。
- 遠位橈尺関節背側脱臼では前腕は回外位となる。
- 手根骨間脱臼は舟状骨骨折と合併することが多い。
- 月状骨脱臼は正中神経を圧迫することが多い。
- 橈骨手根関節脱臼は背側脱臼が多い。
回答はこちらをタップ
1.遠位橈尺関節背側脱臼では前腕は回外位となる。
問題187 第1中手指節関節脱臼について誤っているのはどれか。
- 背側脱臼は母指の背屈・外転が強制されて発生する。
- 掌側脱臼は複合脱臼である。
- 垂直脱臼はZ字型変形を呈する。
- 水平脱臼は観血整復を必要とすることが多い。
回答はこちらをタップ
2.掌側脱臼は複合脱臼である。
問題188 先天性股関節脱臼の徴候でないのはどれか。
- クリックサイン
- テレスコーピングサイン
- フローマンサイン
- トレンデレンブルグサイン
回答はこちらをタップ
3.フローマンサイン
問題189 外傷性股関節後方脱臼について正しいのはどれか。
a.直達外力により発生する。
b.骨頭靭帯の断裂は伴わない。
c.内転・内旋・屈曲位を呈する。
d.大腿骨骨頭壊死が起こりやすい。
- a、b
- a、d
- b、c
- c、d
回答はこちらをタップ
4.c、d
問題190 膝関節脱臼の分類でないのはどれか。
- 上方脱臼
- 前方脱臼
- 後方脱臼
- 側方脱臼
回答はこちらをタップ
1.上方脱臼
問題191 外傷性膝蓋骨脱臼について正しいのはどれか。
- 外側に比べ内側脱臼が多い。
- 内反膝の人に起こりやすい。
- 整復は膝関節を徐々に伸展する。
- 膝関節を屈曲位で固定する。
回答はこちらをタップ
3.整復は膝関節を徐々に伸展する
問題192 習慣性膝蓋骨脱臼の筋力強化で有効なのはどれか。
- 大腿二頭筋
- 大腿四頭筋
- 下腿三頭筋
- 前脛骨筋
回答はこちらをタップ
2.大腿四頭筋
問題193 外傷性距腿関節脱臼で最も多いのはどれか。
- 外方脱臼
- 内方脱臼
- 前方脱臼
- 後方脱臼
回答はこちらをタップ
1.外方脱臼
問題194 ばね指について正しいのはどれか。
- 乳児にはみられない。
- 母指の伸筋腱に多い。
- 中年の女性に多い。
- 腱自体に異常はない。
回答はこちらをタップ
3.中年の女性に多い。
問題195 筋・筋膜性の腰痛について誤っているのはどれか。
- 過度の筋労作が原因である。
- 姿勢保持機構の力学的不均衡は誘因となる。
- 筋肉や筋付着部の疼痛が主な症状である。
- 傍脊柱筋群に筋緊張の低下がみられる。
回答はこちらをタップ
4.傍脊柱筋群に筋緊張の低下がみられる。
問題196 半月板損傷の検査法はどれか。
a.マックマレー検査 b.側方動揺検査 c.ラックマン検査 d.アプレー検査
- a、b
- a、d
- b、c
- c、d
回答はこちらをタップ
2.a、d
問題197 アキレス腱断裂で誤っているのはどれか。
- つま先立ちは可能である。
- 歩行は可能である。
- 断裂部に陥凹を触知する。
- 固定は尖足位とする。
回答はこちらをタップ
1.つま先立ちは可能である。
問題198 足関節捻挫で損傷しやすいのはどれか。
- 前距腓靭帯
- 前脛腓靭帯
- 脛踵靭帯
- 踵腓靭帯
回答はこちらをタップ
1.前距腓靭帯
問題199 25歳の男性。ラグビー中にタックルされ転倒した際に膝外反が強制された。膝関節の疼痛が著名である。最も考えられる外傷はどれか。
- 脛骨外側顆骨折
- 内側側副靭帯損傷
- 脛骨結節剥離骨折
- 前十字靭帯損傷
回答はこちらをタップ
2.内側側副靭帯損傷
問題200 20歳の男性。柔道の乱取り中に、右膝関節部に前方より外力が加わり受傷した。症状として脛骨の後方落ち込み(サギング)がみられた。最も考えられる外傷はどれか。
- 前十字靭帯損傷
- 後十字靭帯損傷
- 外側半月板損傷
- 内側半月板損傷
回答はこちらをタップ
2.後十字靭帯損傷
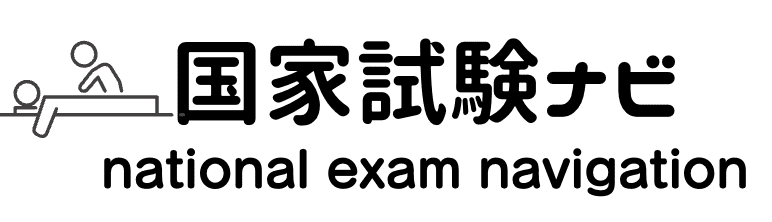

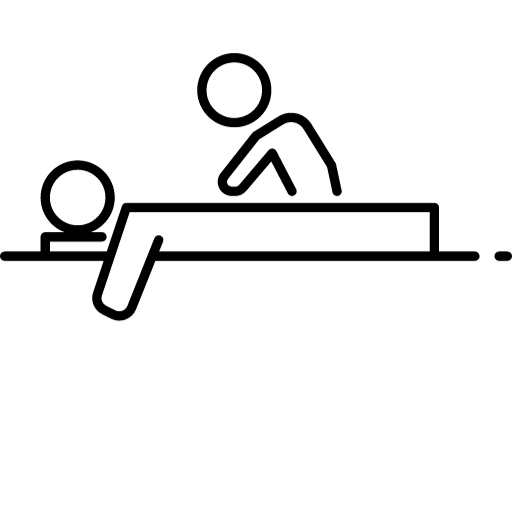








コメント