柔道整復師の国家試験に挑戦しようと考えている人の多くが、まず気になるのが「合格率」です。試験の難易度や出題傾向、合格基準は年々変化しており、情報が整理されていないと不安に感じる方も多いのではないでしょうか。特に再受験を考えている人や、仕事と両立しながら学習している人にとっては、効率的な勉強方法や合格戦略を早めに知ることが重要になります。
本記事では、柔道整復師国家試験の合格率を最新のデータとともに紹介し、合格ラインの目安や効果的な学習法までを網羅的に解説します。合格の可能性を冷静に見極めながら、自信を持って勉強を進められるよう、現実的な情報と具体的なヒントをお届けします。
このページでわかること
- 柔道整復師国家試験の最新合格率と過去の推移
- 新卒・既卒での合格率の違いと受験者傾向
- 合格ラインや出題傾向、試験の構成内容
- 効果的な勉強法とスケジュールの立て方
柔道整復師国家試験の合格率の実態

柔道整復師国家試験は、受験者数や合格率が年々変動しています。特に、新卒と既卒での合格率の差が大きく、受験者の背景によって結果が大きく異なる傾向があります。
以下では、直近の合格率データや過去の推移、新卒・既卒別の合格率の違いについて詳しく見ていきます。
直近の柔道整復師国家試験の合格率
2025年に実施された第33回柔道整復師国家試験の結果は以下の通りです。
| 受験者区分 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 全体 | 4,513名 | 2,607名 | 57.8% |
| 新卒 | 3,188名 | 2,419名 | 75.9% |
| 既卒 | 1,325名 | 188名 | 14.2% |
このデータから、新卒受験者の合格率が高い一方で、既卒受験者の合格率が著しく低いことがわかります。既卒者にとっては、再受験に向けた対策が重要となります。
過去10年の合格率推移から見る傾向
過去10年間の柔道整復師国家試験の合格率は以下の通りです。
| 試験回(年度) | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 第24回(2016年) | 6,164名 | 4,054名 | 65.8% |
| 第25回(2017年) | 6,321名 | 3,690名 | 58.4% |
| 第26回(2018年) | 6,154名 | 3,451名 | 56.1% |
| 第27回(2019年) | 6,164名 | 4,054名 | 65.8% |
| 第28回(2020年) | 5,270名 | 3,401名 | 64.5% |
| 第29回(2021年) | 4,521名 | 2,244名 | 49.6% |
| 第30回(2022年) | 5,027名 | 3,337名 | 66.4% |
| 第31回(2023年) | 4,521名 | 2,244名 | 49.6% |
| 第32回(2024年) | 5,027名 | 3,337名 | 66.4% |
| 第33回(2025年) | 4,513名 | 2,607名 | 57.8% |
この推移を見ると、合格率は年によって大きく変動していることがわかります。特に、2018年以降は60%前後で推移しており、試験の難易度が高まっていることが伺えます。
新卒・既卒で合格率に違いはあるか?
新卒と既卒での合格率には大きな差があります。以下は、直近5年間の新卒・既卒別の合格率です。
| 試験回(年度) | 新卒合格率 | 既卒合格率 |
|---|---|---|
| 第29回(2021年) | 85.6% | 21.6% |
| 第30回(2022年) | 81.0% | 16.9% |
| 第31回(2023年) | 65.4% | 11.5% |
| 第32回(2024年) | 84.0% | 35.9% |
| 第33回(2025年) | 75.9% | 14.2% |
このデータから、新卒受験者の合格率が一貫して高い一方で、既卒受験者の合格率は低く、特に第31回では11.5%と非常に低い数値となっています。
既卒者が合格するためには、計画的な学習と対策が必要です。
柔道整復師国家試験の合格基準と試験内容
柔道整復師国家試験を攻略するには、合格ラインや試験の配点構成、出題傾向を把握することが不可欠です。ここでは、試験の概要から、科目ごとのポイント、必須問題と一般問題の違いといった重要事項までを具体的に解説します。
国家試験の合格ラインと配点構成
国家試験の合格基準は以下の2つの条件を満たすことです。
- 必須問題:得点率80%以上(満点50点中40点以上)
- 全体得点:総得点の60%以上
試験は、必須問題50問・一般問題200問の合計250問で構成され、1問1点の配点となります。下記の配点構成をご覧ください。
| 出題区分 | 問題数 | 配点 |
|---|---|---|
| 必須問題 | 50問 | 50点 |
| 一般問題 | 200問 | 200点 |
| 合計 | 250問 | 250点 |
特に必須問題は「足切り」があり、全体の得点が高くても必須で基準を満たさないと不合格になるため注意が必要です。
問題数が第28回から変わっています。それに伴い問題の傾向も変わっている箇所があるので気をつけましょう。

科目別の出題傾向と学習ポイント
柔道整復師国家試験は9科目に分類され、毎年出題傾向にやや変化はあるものの、基本的な構成は以下の通りです。
| 科目 | 出題の特徴 | 対策のポイント |
|---|---|---|
| 解剖学 | 骨・筋・神経の名称と部位、構造 | 図解を活用しながら反復暗記 |
| 生理学 | 内臓や神経系の機能、反応 | 因果関係と働きの仕組みをセットで覚える |
| 一般臨床医学 | 病名と症状の組み合わせ | 疾患ごとの典型例を抑える |
| 外科学概論 | 手術、外傷処置の基本 | 応急処置や外傷名の定義を確実に |
| 整形外科学 | 運動器疾患やリハビリ関連 | 臨床現場でのイメージを持ちながら学習 |
| リハビリテーション医学 | 機能訓練や回復手段 | 高齢者・障害者に対する介入法を理解 |
| 柔道整復理論 | 骨折・脱臼・捻挫などの理論 | 図や模型を使ってイメージ化 |
| 衛生学・公衆衛生 | 疫学や予防医学の基礎 | 統計や時事問題の出題にも注意 |
| 関係法規 | 柔道整復師法・医療制度など | 最新の法改正や制度内容も確認 |
科目によって出題形式や難易度にばらつきがあるため、不得意分野は重点的に対策し、バランスよく得点できる体制を作りましょう。
必須問題と一般問題の対策
必須問題と一般問題では、出題傾向と学習アプローチが異なります。
- 必須問題
↳正答が明確な基礎的知識を問う問題が中心。確実に点を取る必要があり、過去問の繰り返し学習が効果的 - 一般問題
↳応用力や判断力が求められる。文章量が多く、選択肢のひっかけもあるため、問題慣れが重要
必須問題対策には「暗記力と精度」が求められ、一般問題対策には「慣れと読解力」が問われます。演習バランスを調整しながら、得点戦略を組み立てましょう。
柔道整復師国家試験を合格するための勉強法
合格率だけでなく、「どうやって勉強するか」も合否を左右する大きな要因です。
ここでは、柔道整復師国家試験に合格した人たちが実践していたスケジュール管理や教材の選び方、生活との両立方法について詳しく解説します。
勉強スケジュールの立て方と時間配分
試験対策は「いつから」「どれだけ」勉強を始めるかが重要です。
目安として、3か月〜6か月の学習期間で合格を目指すのが一般的です。
| 期間 | 主な内容 | 学習時間目安 |
|---|---|---|
| 6〜4か月前 | 全科目のインプット(教科書・講義) | 1日2〜3時間 |
| 3〜2か月前 | 過去問演習・模試 | 1日3〜4時間 |
| 1か月前〜直前 | 苦手科目の集中対策・総復習 | 1日5時間以上 |
特に直前期は過去問のやりこみとアウトプット中心の学習が効果的です。
過去問・模試・動画講座の活用方法
合格者の多くが活用しているのが「過去問」と「模試」です。さらに最近はYouTubeや動画講座も定番ツールとなっています。
- 過去問
↳5〜10年分を5周以上。解説を読み込み「なぜその答えになるのか」を理解する - 模試
↳時間配分や実践感覚のトレーニングに有効。全国模試で自分の位置を把握 - 動画講座(YouTube・オンライン予備校)
↳スキマ時間の学習に最適。苦手分野の補強にも役立つ
「知っている」を「解ける」に変えるには、インプットだけでなくアウトプットの比重を高める必要があります。

合格者の勉強法・体験談に学ぶ
合格者に共通しているポイントは、以下のような勉強法と生活習慣です。
- 計画的な学習スケジュール
↳勉強する曜日・時間帯を固定して習慣化 - 苦手科目の優先対策
↳苦手を後回しにせず、最初に取り組む - 学習環境の工夫
↳図書館・カフェなど集中できる場所で勉強 - SNSでの情報収集・励まし合い
↳「勉強垢」で仲間とつながり、継続のモチベ維持
焦りや不安を感じるのは自然なことですが、行動し続けた人こそが最終的に合格を勝ち取っています。
仕事・バイトと両立できる勉強術
働きながら試験に合格する人も多数います。限られた時間の中でも成果を出すためのポイントはこちら。
- 早朝や通勤時間の活用
↳動画講義や暗記アプリでインプット - 休日は「集中デー」に設定
↳1日4〜6時間をまとめて勉強に充てる - スキマ時間にミニテスト形式で復習
↳アプリや単語カードを活用 - 生活リズムを一定に保つ
↳睡眠と食事を整えることで集中力が安定
「時間がない」ではなく、「時間をどう使うか」が合否のカギを握っています。
まとめ|柔道整復師合格への現実的な道筋
柔道整復師国家試験は、決して簡単な試験ではありません。しかし、正しい情報をもとに戦略的に学習を進めることで、多くの受験生が合格を勝ち取っています。
この記事では、合格率の実態から新卒・既卒の傾向、試験内容と出題傾向、そして具体的な勉強法や合格後の進路までを包括的に解説しました。
特に、勉強スケジュールの管理や、過去問・模試の活用、生活との両立といった日々の工夫が合否を分けるポイントになります。
今すぐすべてを完璧にこなす必要はありませんが、「一歩ずつでも行動を積み重ねること」が合格への最短ルートです。焦らず着実に、自分のペースで合格を目指して進んでいきましょう。
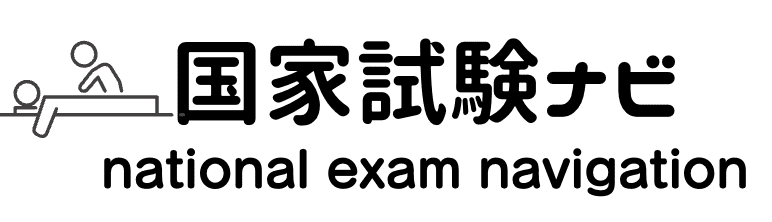
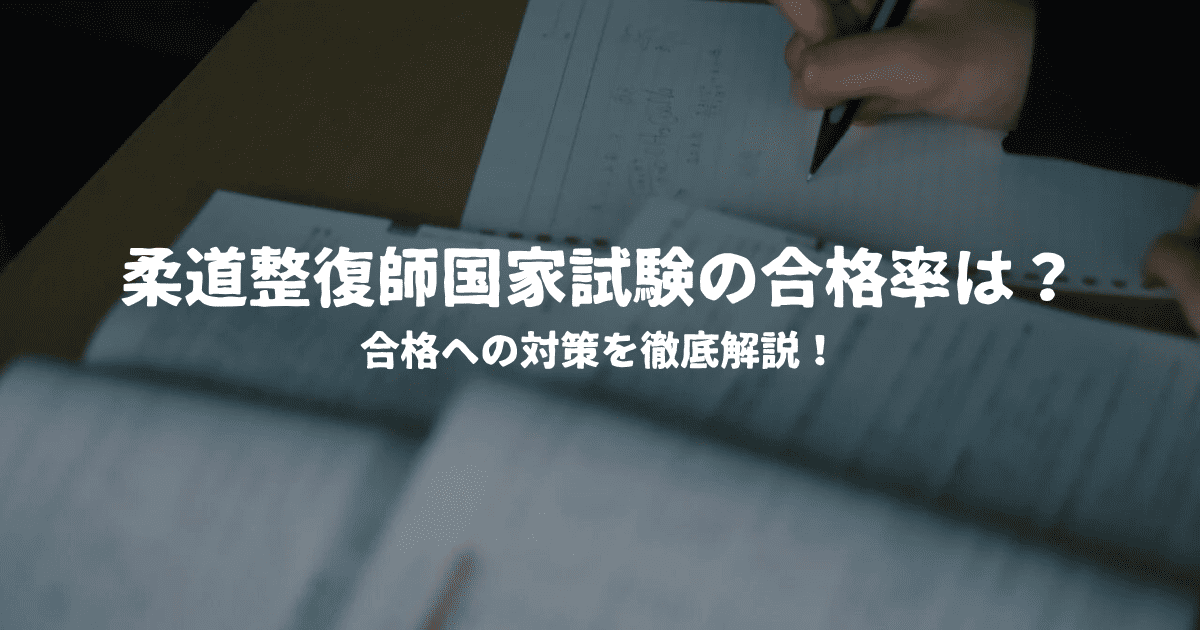
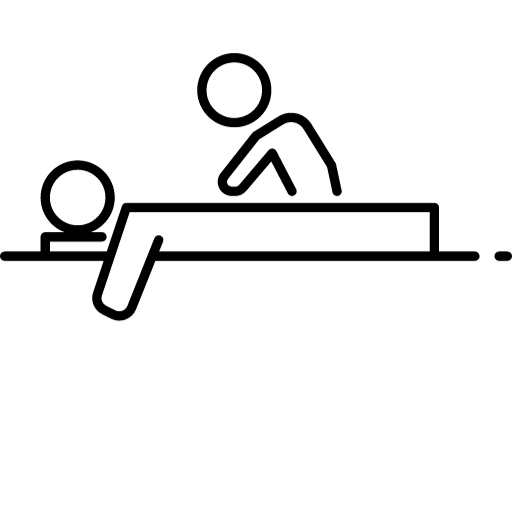
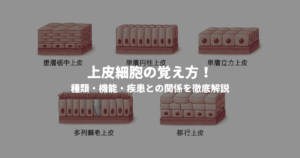
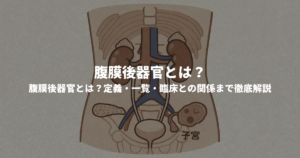


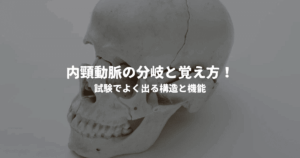
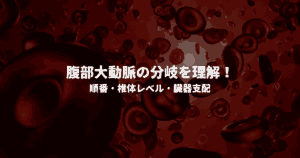

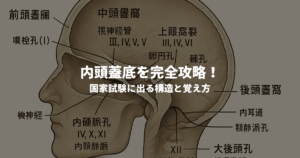
コメント