柔道整復師国家試験、外科学部分別問題輸血・輸液の範囲になります。
輸血・輸液の問題は問題数が多いですが似たような問題が多いイメージです。血液型判定の問題の出題数が多い感覚があります、分野としては難しいので繰り返し学習しましょう。
この過去問を利用してぜひ学習してください。
目次
外科学:輸血・輸液
問題122 輸血について正しいのはどれか。
- 血液型判定はABO式による検査のみで決定される。
- 不適合輸血が行われても注入速度か遅ければ無症状である。
- 成分輸血とは血液中の赤血球、血小板、顆粒球、血漿を分離し、病態に応じて輸注することをいう。
- 新鮮血とは採血後1週間以内のものをいう。
回答はこちらをタップ
3.成分輸血とは血液中の赤血球、血小板、顆粒球、血漿を分離し、病態に応じて輸注することをいう。
問題130 輸血、輸液について正しいのはどれか。
- 輸血の際、患者と供血者との血液について交差適合試験を行う。
- 出血に伴う電解質の不足が認められた時は成分輸血で補う。
- 電解質輸液を行う時は合併症としての出血傾向に注意すべきである。
- 出血が循環血液量以上の場合は等張ブドウ糖液の輸液を行う。
回答はこちらをタップ
1.輸血の際、患者と供血者との血液について交差適合試験を行う。
問題126 輸血について誤っている組合せはどれか。
- 不適合輸血 ─── 血尿
- 感染 ─── 血清肝炎
- アレルギー ─── AIDS
- 過剰投与 ─── 心不全
回答はこちらをタップ
3.アレルギー ─── AIDS
問題127 輸液剤について誤っている組合せはどれか。
- 血漿 ─── 膠質輸液
- 5%ブドウ糖液 ─── 高浸透圧
- 高カロリー輸液 ─── 栄養補給
- リンゲル液 ─── 電解質輸液
回答はこちらをタップ
2.5%ブドウ糖液 ─── 高浸透圧
問題123 輸血による副作用について誤っているのはどれか。
- 抗原抗体反応
- ウイルス感染
- 高脂血症
- 肝機能障害
回答はこちらをタップ
3.高脂血症
問題123 輸液の目的で誤っているのはどれか。
- 臓器不全時の大量輸液
- 栄養成分の補給
- 膠質浸透圧の是正と維持
- 水分・電解質バランスの是正と維持
回答はこちらをタップ
1.臓器不全時の大量輸液
問題125 輸血について誤っているのはどれか。2つ選べ。
- 血液型判定に使用する抗A血清は青色である。
- ABO式およびRh式血液型が一致すれば交叉試験を省略できる。
- 供血者の血色素量は12g/dl以上が望ましい。
- 保存血とは採血後96時間から21日までのものをいう。
回答はこちらをタップ
2.ABO式およびRh式血液型が一致すれば交叉試験を省略できる。
4.保存血とは採血後96時間から21日までのものをいう
問題152 輸血の副作用で誤っているのはどれか。
- アレルギー反応
- ウイルス感染
- 移植片対宿主反応
- 血糖値上昇
回答はこちらをタップ
4.血糖値上昇
問題168 経静脈的高カロリー輸液について正しいのはどれか。
- 蛋白質の補給には主として血漿を用いる。
- 消化管の術後で長期間経口摂取できないときに行う。
- 輸液はまず50%糖液から始める。
- 末梢静脈から注入する。
解答はこちらをタップ
2.消化管の術後で長期間経口摂取できないときに行う。
問題167 血清電解質濃度で正常値でないのはどれか。
- Na116mEq/l
- K4.3mEq/l
- Cl101mEq/l
- Ca10.2mg/dl
解答はこちらをタップ
1.Na116mEq/l
問題167 輸血で誤っているのはどれか。
- 血液型が同じでも交差適合試験を行う。
- 成分輸血を行う。
- 不適合輸血の死亡率は低い。
- 肝炎などの感染症が発症する。
解答はこちらをタップ
3.不適合輸血の死亡率は低い。
問題170 不適合輸血による初期症状で正しいのはどれか。
- 肝炎
- 下腿浮腫
- 無尿
- 発疹
解答はこちらをタップ
4.発疹
問題167 輸血の副作用で正しいのはどれか。
- 滴下速度と無関係に発生する。
- 移植片対宿主反応(GVHD)がある。
- 発疹は出現すると長時間持続する。
- 腎不全は不適合輸血直後に起こる。
解答はこちらをタップ
2.移植片対宿主反応(GVHD)がある。
問題168 輸血の副作用と症状の組合せで正しいのはどれか。
- 空気塞栓-乏尿
- 不適合輸血-血圧低下
- クエン酸中毒-発熱
- ウイルス感染-けいれん
解答はこちらをタップ
2.不適合輸血-血圧低下
問題167 輸血で正しいのはどれか。
- 採血後6日以内のものを新鮮血という。
- 保存血輸血は血小板の補給が期待できる。
- 凝固因子の補充には新鮮凍結血漿を用いる。
- 循環血液量の維持には血小板輸血を用いる。
解答はこちらをタップ
3.凝固因子の補充には新鮮凍結血漿を用いる。
問題178 輸血で正しいのはどれか。
- 血漿交換は劇症肝炎に有効である。
- 新鮮血輸血では凝固因子の補給ができない。
- 保存血輸血では血小板の補給が期待できる。
- 血小板輸血は循環血漿量の補充に用いる。
回答はこちらをタップ
1.血漿交換は劇症肝炎に有効である。
問題178 輸血する際の指標で誤っているのはどれか。
- 血 圧
- 呼吸数
- 尿 量
- 中心静脈圧
回答はこちらをタップ
2.呼吸数
問題 178 抗原抗体反応(不適合輸血)の早期症状で誤っているのはどれか。
- 発熱
- 発疹
- けいれん
- 悪心・嘔吐
解答はこちらをタップ
3. けいれん
まとめ
輸血・輸液の範囲では難しい問題が多く、知識として覚えておかなくてはならない問題が多い印象です。
特に輸液の問題が難しいので問題を何度も繰り返し勉強し、教科書も読んでおくと良いと思います。
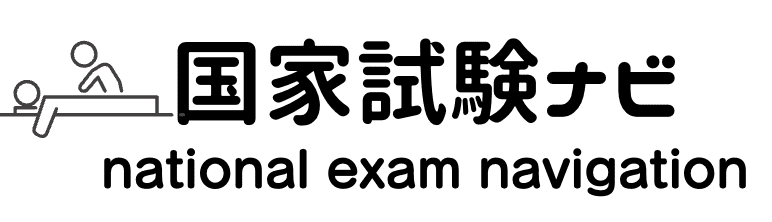
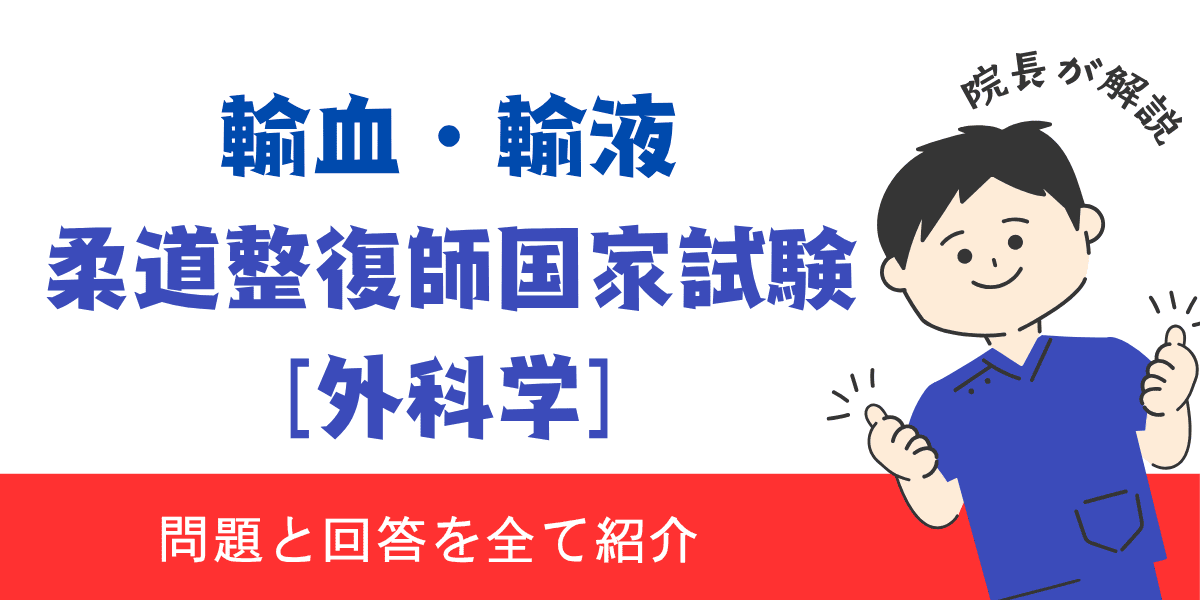
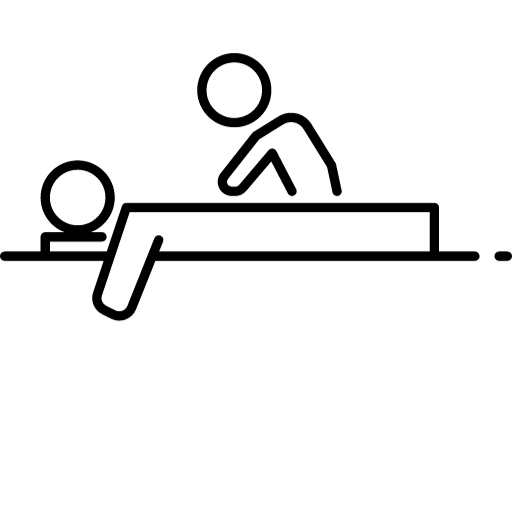
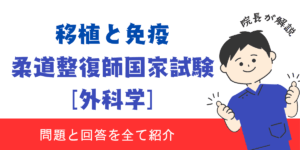







コメント