柔道整復師国家試験、衛生学・公衆衛生学の部分別問題疾病の生活環境・食品衛生範囲になります。
この範囲では食中毒の問題が多く出題されています。特に菌の名前が多く出題されるので覚えて絵おくようにしておきましょう。
この過去問を利用してぜひ学習してください。
衛生・公衆衛生学:生活環境・食品衛生
問題81 我が国の上水について正しいのはどれか。
- 浄水法の薬品沈澱で用いる薬品は塩素である。
- 水道の末端の残留遊離塩素の量は0.4ppm以上とされている。
- 飲料水の水質基準では大腸菌群は証明されてはならない。
- Ca、Mgを炭酸塩、硫酸塩の形で多く含んでいる水を軟水という。
回答はこちらをタップ
3.飲料水の水質基準では大腸菌群は証明されてはならない。
問題82 我が国の下水について正しいのはどれか。
- 下水の好気的処理法にはイムホフ槽がある。
- 下水道の最近の普及率は95%である。
- 下水のBODが高いことは汚染度が低いことを意味する。
- 下水道の施設には分流式、合流式および混合式がある。
回答はこちらをタップ
4.下水道の施設には分流式、合流式および混合式がある。
問題87 我が国の最近の栄養摂取状態について誤っているのはどれか。
- 穀類摂取が減少し、動物性蛋白質や油脂の摂取量が増加している。
- ビタミン摂取量は栄養所要量をほぼ充足している。
- 食塩摂取量の目標は10g/日以下である。
- カルシウムは栄養所要量を上回っている。
回答はこちらをタップ
4.カルシウムは栄養所要量を上回っている。
問題81 水道水の水質基準で許容量が規定されている物質はどれか。
- 鉛
- シアンイオン
- 水銀
- 有機リン
回答はこちらをタップ
- 鉛
- シアンイオン
- 水銀
問題83 食中毒の原因について誤っている組合せはどれか。
- 腸炎ビブリオ ─── 好塩菌
- サルモネラ菌 ─── エクソトキシン
- ボツリヌス菌 ─── 好気性菌
- ブドウ球菌 ─── エンテロトキシン
回答はこちらをタップ
2.サルモネラ菌 ─── エクソトキシン
3.ボツリヌス菌 ─── 好気性菌
問題84 住居環境について誤っているのはどれか。
- カタ温度計で空気の冷却力を測定する。
- 実効温度は乾球温度および湿球温度から算出する。
- 窓の面積は床面積の20%以上が良い。
- 室内外の温度差で自然換気が起こる。
回答はこちらをタップ
2.実効温度は乾球温度および湿球温度から算出する。
問題81 水道法で規定する水質基準はどれか。
- BOD(生物的酸素要求量)
- COD(化学的酸素要求量)
- pH(水素イオン濃度)
- DO(溶存酸素)
回答はこちらをタップ
3.pH(水素イオン濃度)
問題89 食中毒の原因となるのはどれか。
- エンテロウイルス
- リケッチア
- 腸炎ビブリオ
- スピロヘータ
回答はこちらをタップ
3.腸炎ビブリオ
問題87 上水道について正しいのはどれか。
- 普及率は全国平均で47%である。
- 1人1日平均使用量は年々減少している。
- 水道水の消毒はアルコール消毒がよい。
- 大腸菌群は検出されてはならない。
回答はこちらをタップ
4.大腸菌群は検出されてはならない。
問題88 廃棄物について正しいのはどれか。
- 一般廃棄物の1人1日当たりの排出量は最近横ばいである。
- 一般廃棄物処理では焼却が2割である。
- し尿処理では農村還元が最も多い。
- 産業廃棄物の処理は市区町村長の責任で行われる。
回答はこちらをタップ
1.一般廃棄物の1人1日当たりの排出量は最近横ばいである。
問題83 食中毒の原因として誤っているのはどれか。※解なし
- 腸炎ビブリオ
- 赤痢菌
- PCB
- テトロドトキシン
回答はこちらをタップ
問題84 水道法による水質基準で検出されてはならないのはどれか。
- 大腸菌
- 六価クロム
- 水銀
- シアン
回答はこちらをタップ
1.大腸菌
問題85 感染性廃棄物の処理について正しいのはどれか。
- 包装すれば一般廃棄物と一緒に処理してよい。
- 自家の焼却炉で焼却してはいけない。
- 専門の処理業者に委託してはいけない。
- オートクレーブで滅菌したガーゼは一般廃棄物と一緒に処理してよい。
回答はこちらをタップ
4.オートクレーブで滅菌したガーゼは一般廃棄物と一緒に処理してよい
問題87 住居環境で誤っているのはどれか。
- 必要換気量は30m3/時である。
- 気積は10m3である。
- 採光の開角は最小限28度である。
- 屋内気温は22~25℃がよい。
回答はこちらをタップ
2.気積は10m3である。
問題89 下水処理で正しいのはどれか。
- 活性汚泥法は嫌気性菌を用いる。
- 消化槽は有機固型物を処理する。
- 処理水は検査しないで放流する。
- 生物化学的酸素要求量は測定しない。
回答はこちらをタップ
2.消化槽は有機固型物を処理する。
問題82 医療機関から出されるガーゼの処理について正しいのはどれか。
- 滅菌すれば一般廃棄物として処理できる。
- トリアージタッグをつけて廃棄しなければならない。
- 処理業者は市町村長の認可を受けなければならない。
- 処分を委託した後は排出者に責任はない。
解答はこちらをタップ
1.滅菌すれば一般廃棄物として処理できる。
問題85 高血圧が発症のリスク要因となる疾患はどれか。
a.虚血性心疾患 b.脳血管疾患 c.リウマチ性心疾患 d.糖尿病
- a、b
- a、d
- b、c
- c、d
回答はこちらをタップ
1.a、b
問題86 食中毒の潜伏期問が最も短いのはどれか。
- 黄色ブドウ球菌
- サルモネラ菌
- ボツリヌス菌
- 腸炎ビブリオ
回答はこちらをタップ
1.黄色ブドウ球菌
問題81 上水道について誤っているのはどれか。
- 普及率(給水人口/総人口)は90%を超えている。
- トリハロメタンは浄水処理中に生成される。
- 上水末端における遊離残留塩素は0.1ppm以上と定められている。
- 大腸菌群は100/ml以下と定められている。
回答はこちらをタップ
4.大腸菌群は100/ml以下と定められている。
問題84 誤っている組合せはどれか。
- 腸炎ビブリオ ─── 感染型食中毒
- 黄色ブドウ球菌 ─── 耐熱性毒素
- サルモネラ菌 ─── 毒素型食中毒
- ボツリヌス菌 ─── 神経性毒素
回答はこちらをタップ
3.サルモネラ菌 ─── 毒素型食中毒
問題81 居住環境について誤っているのはどれか。
- 室内の空気汚染の指標として二酸化炭素濃度が用いられる。
- 自然換気は室内外の温度差と外気の風力によって生じる。
- 室内の気流が増せば感覚温度は下がる。
- 採光における入射角は最小限4~5度を必要とする。
回答はこちらをタップ
4.採光における入射角は最小限4~5度を必要とする
問題94 食中毒で誤っているのはどれか。
- 腸炎ビブリオは感染型の食中毒を起こす。
- 近年食中毒患者は著しく減少している。
- 食品中の化学物質は食中毒の原因となる。
- フグ毒は神経を麻痺させる。
回答はこちらをタップ
2.近年食中毒患者は著しく減少している。
問題110 住居環境について誤っているのはどれか。
- 室内の二酸化炭素濃度が0.1%を超えたら換気をする。
- 冬期の室内温度22~23℃に設定する。
- 昼光率は1%以上あれば良好である。
- 室内気流をアスマン通風乾湿温度計を使い測定する。
回答はこちらをタップ
4.室内気流をアスマン通風乾湿温度計を使い測定する。
問題111 水道法による水質基準について誤っているのはどれか。
- 硝酸性および亜硝酸性窒素は、し尿由来の有機物汚染の指標である。
- 大腸菌群は病原性微生物汚染の指標である。
- 塩素イオンは消毒に使われた塩素濃度の指標である。
- 過マンガン酸カリウム消費量は有機物汚染の指標である。
回答はこちらをタップ
1.硝酸性および亜硝酸性窒素は、し尿由来の有機物汚染の指標である。
問題117 食品衛生について正しいのはどれか。2つ選べ。
- 栄養指導の基準である栄養所要量は毎年改定される。
- 食品衛生監視員が食品関係営業施設の監視や指導を行う。
- 食品への有害物混入による健康被害は食中毒に分類される。
- 黄色ブドウ球菌による食中毒は食品の加熱処理で防止できる。
回答はこちらをタップ
2.食品衛生監視員が食品関係営業施設の監視や指導を行う。
3.食品への有害物混入による健康被害は食中毒に分類される。
問題112 住居環境について正しいのはどれか。
- 夏の家屋内気温は22~23℃が適切である。
- 必要換気量は1人1時間あたり33m3である。
- 家屋内二酸化炭素の濃度は1.0%が基準である。
- 採光で入射角は4~5度であればよい。
解答はこちらをタップ
2.必要換気量は1人1時間あたり33m3である。
問題113 下水処理について誤っているのはどれか。
- 活性汚泥中の好気性菌は有機物を分解浄化する。
- 合併処理浄化槽では嫌気性菌を利用する。
- 好気性処理で汚水中のリンが除去される。
- 処理された水は水質検査後放流される。
解答はこちらをタップ
3.好気性処理で汚水中のリンが除去される。
問題114 感染性廃棄物処理について正しいのはどれか。
- 包装すれば一般廃棄物と一緒に処理してよい。
- 病院の焼却炉で焼却してはいけない。
- 専門の処理業者に委託してはいけない。
- 焼却炉で滅菌した注射針は感染性廃棄物として処理する。
解答はこちらをタップ
1.包装すれば一般廃棄物と一緒に処理してよい。
問題117 毒素型食中毒の原因になるのはどれか。
- サルモネラ属菌
- カンピロバクター
- 腸炎ビブリオ
- 黄色ブドウ球菌
回答はこちらをタップ
4.黄色ブドウ球菌
問題113 生活習慣病で誤っているのはどれか。
- 脳血管疾患のリスク要因として高血圧が指摘されている。
- 大腸がんは食習慣との関連が指摘されている。
- 2型糖尿病は運動習慣との関連が指摘されている。
- 虚血性心疾患の抑制因子として低比重リポ蛋白(LDL)血症が指摘されている。
解答はこちらをタップ
4.虚血性心疾患の抑制因子として低比重リポ蛋白(LDL)血症が指摘されている。
問題115 誤っているのはどれか。
- 我が国の食料の輸入割合はエネルギーベースで50%以下である。
- 2005年に「日本人の栄養所要量」は「日本人の食事摂取基準」と改められた。
- 健康増進法において健康の増進に努めることは国民の責務となっている。
- 食育とは健全な食生活を実践できるようにする教育である。
解答はこちらをタップ
1.我が国の食料の輸入割合はエネルギーベースで50%以下である。
問題120 正しいのはどれか。2つ選べ。
- 上水の基準は環境基本法による。
- 上水には大腸菌を検出してはならない。
- 上水末端においては塩素が残留してはならない。
- 上水処理中に発生したトリハロメタンは発がん物質である。
解答はこちらをタップ
2.上水には大腸菌を検出してはならない。
4.上水処理中に発生したトリハロメタンは発がん物質である。
問題113 毒素型細菌性食中毒を起こすのはどれか。2つ選べ。
- ウェルシュ菌
- 病原大腸菌
- ボツリヌス菌
- カンピロバクター
解答はこちらをタップ
1.ウェルシュ菌
3.ボツリヌス菌
問題118 屋内気候の基準でないのはどれか。
- 温度
- 湿度
- 気流
- 不快指数
解答はこちらをタップ
4.不快指数
問題119 上水道で誤っているのはどれか。
- 水道法に基づき水質基準が定められている。
- 浄水処理には沈殿、ろ過、消毒の工程がある。
- 硝酸態窒素は各種の病原菌による汚染の指標である。
- 塩素と原水中の有機物質からトリハロメタンが発生する。
解答はこちらをタップ
3.硝酸態窒素は各種の病原菌による汚染の指標である。
問題119 水道法による水質基準で検出されてはならないのはどれか。
- 塩化物イオン
- 硝酸態(性)および亜硝酸態(性)窒素
- 大腸菌
- 遊離残留塩素
解答はこちらをタップ
3.大腸菌
問題120 廃棄物処理の理念で「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に規定されていないのはどれか。
- 再生の抑制
- 処理施設の確保
- 適正処理の確保
- 廃棄物の減量化
解答はこちらをタップ
1.再生の抑制
問題112 肝癌の危険因子で誤っているのはどれか。
- 喫煙
- 飲酒
- コーヒー摂取
- 肥満
解答はこちらをタップ
3.コーヒー摂取
問題113 毒素型の食中毒を起こす原因菌はどれか。
- 病原大腸菌
- サルモネラ菌
- ボツリヌス菌
- カンピロバクター
解答はこちらをタップ
3.ボツリヌス菌
問題119 事務所の屋内空気の衛生環境基準で誤っているのはどれか。
- 気積-10㎥/人以上
- 湿度-40〜70%
- 気流-0.5m/秒以上
- 浮遊粉じん-0.15mg/㎥以下
解答はこちらをタップ
3.気流-0.5m/秒以上
問題113 微量で生体内の代謝や生理機能を調整するのはどれか。
- 糖質
- 食物繊維
- 蛋白質
- ビタミン
解答はこちらをタップ
4.ビタミン
問題119 値が大きい方が水質汚濁の程度が低い指標はどれか。
- 浮遊物質(SS)
- 溶存酸素(DO)
- 化学的酸素要求量(COD)
- 生物化学的酸素要求量(BOD)
解答はこちらをタップ
2.溶存酸素(DO)
問題119 医療施設から出る体液で汚染された廃棄物が該当するのはどれか。
- 一般廃棄物
- 産業廃棄物
- 放射性廃棄物
- 特別管理廃棄物
解答はこちらをタップ
4.特別管理廃棄物
問題115 毒素型食中毒の原因となるのはどれか。
- コレラ菌
- ノロウイルス
- 黄色ブドウ球菌
- 腸管出血性大腸菌
回答はこちらをタップ
3.黄色ブドウ球菌
問題120 水道法に基づく水質基準で検出されてはならないのはどれか。
- ヒ素
- 大腸菌
- カドミウム
- 総トリハロメタン
回答はこちらをタップ
2.大腸菌
問題115 平成28年の食中毒統計において、発生件数の多い原因はどれか。2つ選べ。
- サルモネラ菌
- ノロウイルス
- ボツリヌス菌
- カンピロバクター
解答はこちらをタップ
2.ノロウイルス
4.カンピロバクター
問題134 食中毒で正しいのはどれか。
- キノコは食中毒の原因となる。
- 近年の我が国では黄色ブドウ球菌による件数が最も多い。
- ボツリヌス菌は感染型の食中毒を起こす。
- 食品を低温で保存すれば細菌は死滅する。
回答はこちらをタップ
1.キノコは食中毒の原因となる。
問題140 廃棄物処理法に基づく廃棄物の取り扱いで誤っているのはどれか。
- 産業廃棄物の処理の責任は事業者にある。
- 家庭で飼っていた動物の死体は一般廃棄物として扱う。
- 特別管理産業廃棄物の委託処理に管理票(マニフェスト)を使用する。
- 医療機関において体液に汚染されたガーゼは一般ごみと共に廃棄してよい。
回答はこちらをタップ
4.医療機関において体液に汚染されたガーゼは一般ごみと共に廃棄してよい。
問題140 水質汚濁の指標に含まれないのはどれか。
- 硬度
- 浮遊物質
- 溶存酸素
- 水素イオン濃度
回答はこちらをタップ
1.硬度
問題140 上水で正しいのはどれか。2つ選べ。
- 上水の基準は環境基本法による。
- 上水には大腸菌を検出してはならない。
- 上水末端においては塩素が残留してはならない。
- 上水処理中に発生したトリハロメタンは発がん物質である。
回答はこちらをタップ
2.上水には大腸菌を検出してはならない。
4.上水処理中に発生したトリハロメタンは発がん物質である。
問題132 国民の健康づくりのための食生活指針において目標とされる1日の野菜摂取量はどれか。
- 150g以上
- 250g以上
- 350g以上
- 450g以上
回答はこちらをタップ
3.350g以上
問題140 感染性廃棄物で正しいのはどれか。2つ選べ。
- 地方自治体で処理する。
- 一般廃棄物として処理する。
- マニフェスト伝票形式によって処理をする。
- 病院で血液に汚染されたガーゼが該当する。
回答はこちらをタップ
3.マニフェスト伝票形式によって処理をする。
4.病院で血液に汚染されたガーゼが該当する。
問題 139 受動喫煙の防止について規定しているのはどれか。
- 環境基本法
- 健康増進法
- 地域保健法
- ダイオキシン類対策特別措置法
解答はこちらをタップ
2. 健康増進法
問題 140 水質で正しいのはどれか。
- CODの環境基準達成率100%である。
- 水道水の水質基準に硬度の項目がある。
- 水道水に一般細菌は検出されてはいけない。
- 水道水に遊離残留塩素は検出されてはいけない。
解答はこちらをタップ
2. 水道水の水質基準に硬度の項目がある。
まとめ
食中毒の問題が多く出題されますが、水質の問題も多く出題されています。ODなどという単語もしっかり復習しておきましょう。
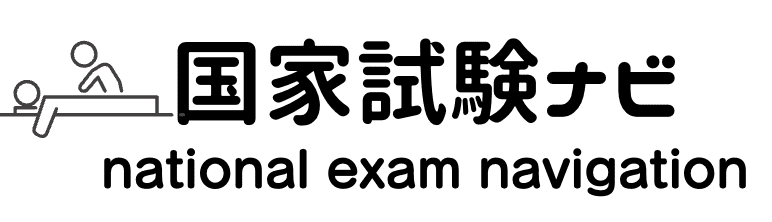
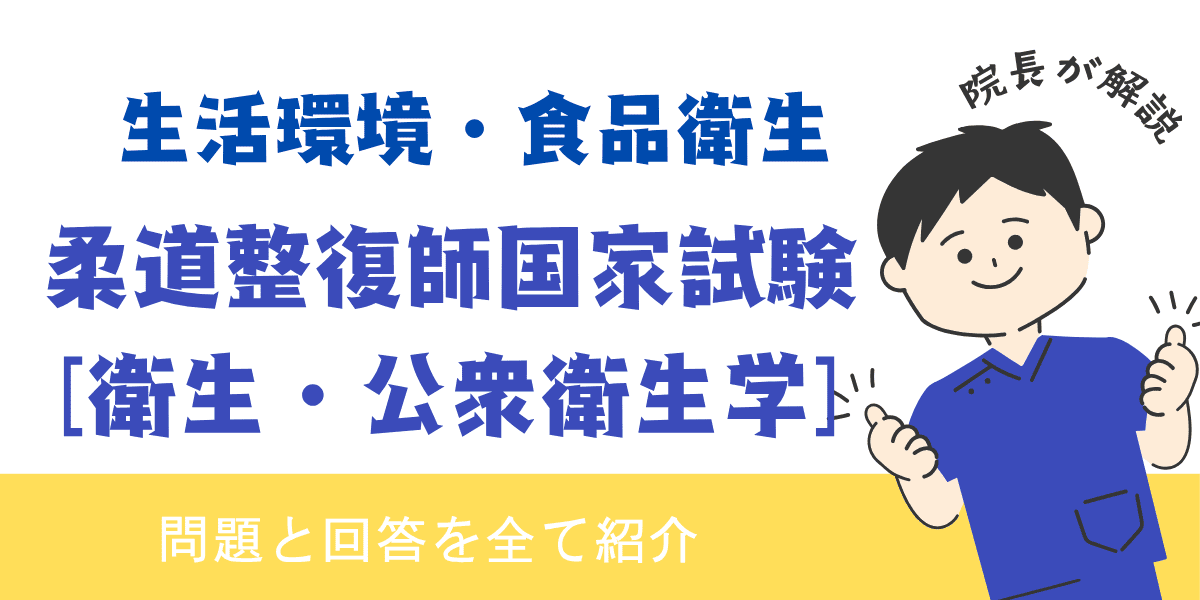
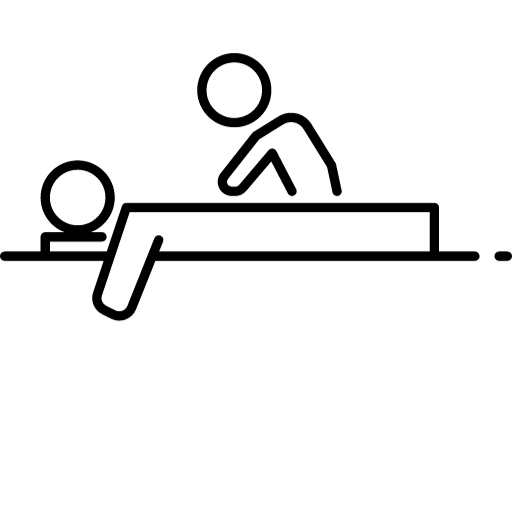
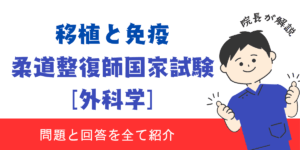







コメント